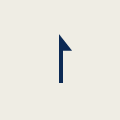第40回「品質を守る開発手法Ⅱ」~DevTeOps~
第39回のコラムで「DevTeOps」について書いたところ、反響をいただきました。
今回は、少し具体的な話を追加します。 「品質を上げるには結局どうすればいいのだ!」という質問に対する回答を「DevTeOps」と定義しました。これは開発(Development)と運用(Operation)それにテスト(Test)が一緒のチームとして協力して開発する手法です。開発と運用にテストを加えた開発スキームです。「なぜテストチームが必要なのか、テストチームはどのような作業ができるのか」について説明します。
品質を支えるテスト技術者
これまでに、「品質を向上させるためには、テストの専門知識を持った技術者がプロジェクトに必要」と説明してきました。
この開発手法のように、立場が異なる技術者が一緒に作業する場合は中立的に判断する技術者が必要です。それがテスト技術者です。開発の視線(製品品質)と運用の視線(利用時の品質)の両方を理解している技術者が重要といえます。
また、テスト実行だけではなく品質を向上させるいろいろな分析が必要となります。

問い合わせ分析から品質向上へ
テスト結果を分析して次の開発で改善すべきポイントを見つける事も重要です。また、運用面でみるとコールセンターへの問い合わせ内容を分析して改善点を見つける事も重要です。
コールセンターの情報は大きく「操作性の質問」「機能の要望」「不具合の質問」の3つに分類できます。操作性に対する質問を分析するとマニュアルの不備が散見されます。記述ミス・記載漏れはわかりやすい内容ですが、そもそも「見づらい」「操作方法が見つけづらい」「検索しづらい」「直感的に操作できない」など相当な件数となります。これを解決するにはマニュアルの見直ししかありません。従来の「画面を貼り付けて操作内容を記述するだけ」のマニュアルでは利用者とっては不十分です。
例えば、想定される標準操作方法の手順が記載され、そこからイレギュラー処理が枝分かれするような構成にすれば、利用者の満足度は上がり、問合せ件数は減ります。結果的に運用コストの削減となります。
このデータは、製品品質特性に分類して分析すると次期の開発にも大いに役立ちます。
例えば、質問の内容がデータの利用にあるとします。Excelを活用して個々に分析したいとの要望が多ければ、「互換性」の機能を充実させるようにします。「入力しづらい」という意見が多ければ「使用性」を重視した改善を図ればよいということになります。
このように、同じデータを異なる視線で分析する事でトータル的に品質を向上する事が可能となります。最終的にはコールセンターへの問合せが減ることでコストダウンとなります。
コールセンターを充実させることが顧客満足度UPと考える経営者がいますが、大きな間違いです。本来は、コールセンターに頼らずともシステム運用ができることが品質の良いシステムです。トータル品質を向上させ、コストダウンに挑戦してください。