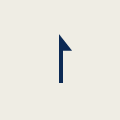第41回「ローカライズとカルチャライズ」
ITの話になると北米欧州が中心となりますが、2016年ごろに大きな動きが出たのが東南アジア諸国連合(以下、ASEAN)です。
ASEAN諸国とIT市場の成長
2016年ごろ、中国のマーケットを目指した日本のIT企業は、オフショアで現地を使うことは出来ましたが、IT製品を売り込む事には全敗と言っていい状況でした。特にソフトウェア分野では、ソースコードの提供を求められるようになってから、進出計画をまったく聞かなくなりました。コラム37号で台湾の事情を書きましたが、台湾企業を経由して販売しようとしたケースはありますが、成功した事例は聞こえてきません。韓国においても言語の問題があり同様の結果になったと聞いています。
その中で急速に注目されてきたのが東南アジアのASEAN諸国です。インドネシア、マレーシア、タイ、カンボジア、ミャンマー、そして、ベトナムも注目されてきました。「ここにインドが加われば、中国以上の巨大マーケットが出現する」という兆しがあり、当時からビジネス的にも注目していました。

海外進出と日本企業の課題
海外進出の注意点は、規格の違いです。コラムのはじめに2層式の洗濯機の話を書きましたが、日本の当時の洗濯機は、回転中でも追加で洗濯物が入れられるように蓋を開けると急停止して安全を担保していました。ところが、諸外国の仕様はそもそも回転中には蓋が開いてはいけない仕様です。それを知らないメーカーが輸出をして大量クレームとなり大きな損害を出した事例もあります。今となっては笑い話です。
現地の仕様に合わせることをローカライズと言いますが、東南アジアのメリットは言語的に英語が通用している点にあります。ホテルでも大型ショッピングセンターでも英語は普通に通じ、IT系では仕様書が英語で表記されていることが大半です。標準規格も欧米準拠となっています。製品を販売しようとした場合のローカライズが比較的容易で、共通化が図りやすいです。
問題がもう一点あります。それは「カルチャライズ」、文化・宗教の違いです。日本でもっともグローバルなソフトウェアはゲームソフトです。世界中で販売できてすごいと思いますが、実は大変な苦労があります。それがカルチャライズです。
例えば、宗教上の理由で肉を食べてはいけない国があります。ゲームの中で肉を食べるシーンがあった場合、それを別のものに変更することが求められます。女性の顔を隠す習慣がある国ではキャラクターの造形に配慮が必要であり、決闘シーンで流血の描写があると禁止される国もあります。色の制限や日本人には想像できない制約などが存在します。これらを書き換える作業がカルチャライズです。これを怠ると、まったく売れない製品となります。

中小企業としてのビジネス展開
中小企業がこうした対応のために、一からすべて調べると莫大な費用が必要です。そこで、業界団体としてマレーシアのテスト事業者と情報交換を行っています。東南アジアではマレーシアを中心に品質の一環としてローカライズとカルチャライズの対応をする検証会社が複数設立されています。東南アジアマーケットに興味を持たれたら、ぜひ調べてみてください。