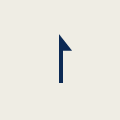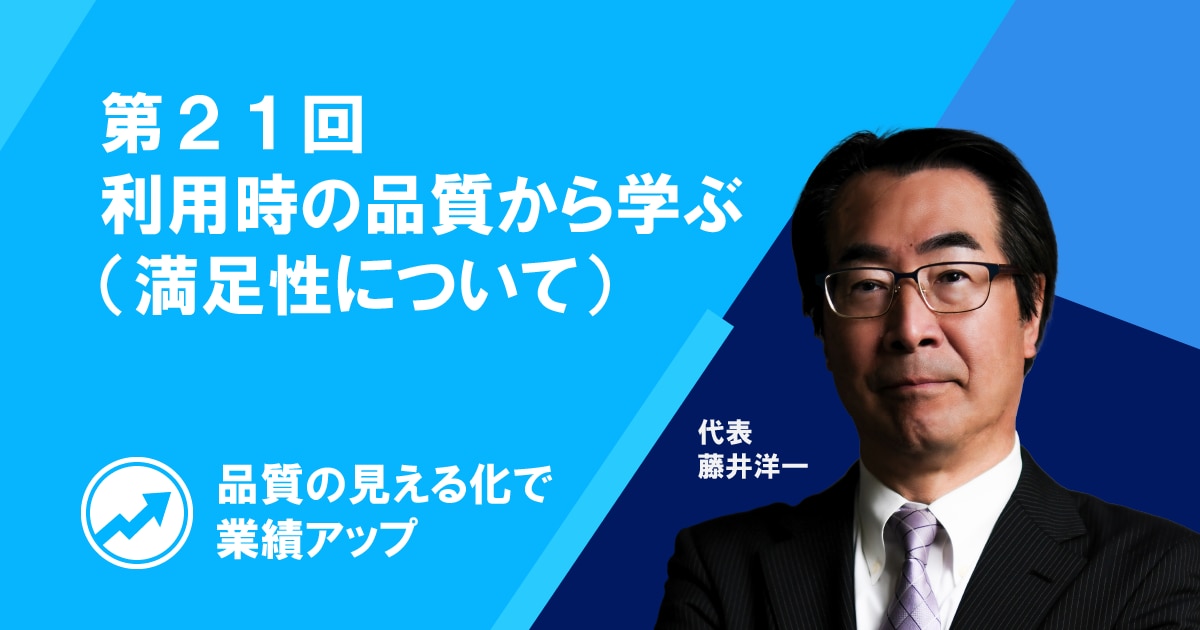
第21回 利用時の品質から学ぶ(満足性について)
前回は利用時の品質の効率性について解説しました。今回は最大の難関である満足性に関して記述します。
品質特性「満足性」について
満足性は「製品又はシステムが明示された利用状況において使用されるとき、利用者ニーズが満足される度合い」と規定されています。解釈としては、たとえば会計システムの場合を考えたとき、利用状況としては会計知識があり仕訳作業ができる利用者、そして「社内ネットワークのクライアント・サーバー環境で利用可能」等が明示された利用状況を想定しています。その上で、利用者が必要とする機能が実装されていて、彼らがどのくらい満足できるかということです。
この満足性という品質特性は非常にあいまいで、測定が難しく評価も難しいです。副特性としては4つの特性が記述されています。
- 実用性
「利用の結果及び利用の影響を含め、利用者が把握した目標の達成状況によって得られる利用者の満足度合い」
解釈としては、そのシステムがカタログ上でいろいろな財務諸表・財務分析が可能と明示していた場合、その帳票の出力内容が利用者から見て期待した結果であり満足した度合いということです。
- 信用性
「利用者又は他の利害関係者がもつ、製品又はシステムが意図したとおりに動作するという確信の度合い」
会計システムで複数の端末から仕訳入力をした場合、試算表を含めた財務諸表がすばやく正確な結果が得られるという信頼感、安心感の度合いを示します。元帳の数値と試算表の数値が一度でも違算するような場合や、動作が停止した場合、信頼性は低下し満足度合いは低くなるということです。
- 快感性
「個人的なニーズを満たすことから利用者が感じる喜びの度合い」
注記として、個人的なニーズには新しい知識及びスキル(技術)を獲得するというニーズ、個人のアイデンティティを伝えるというニーズおよび心地よい記憶を引き起こすニーズを含むことができるとあります。
ただ、快感性に関しては専門家でも解釈が分かれており、私個人的には測定できない領域だと考えています(あえてコメントするならば、初めてPCでオリジナル年賀状を作成したときの感激の度合いのようなものでしょうか)。
- 快適性
「利用者が(システム又はソフトウェアを利用する時)快適さに満足する度合い」
これがエアコンなら「夏は涼しく冬はあたたかい!」と分かりやすく判断できるかもしれませんが、システムにおいての快適性というと、たとえば「サクサク動く」「入力後ただちに結果が見られる」「予測変換がスムーズ」などでしょうか。利用者によって求める快適性は違うと思いますが、おおむねこんな感じ(いい加減なコメントでスミマセン)です。

満足性の測定について
さて、満足性は測定が困難であると冒頭に言いましたが、それでは測定不可能かというとそうではありません。どうするかというと、お客様相談室やコールセンターの情報です。高い満足性の反対には不満足、つまり苦情やクレームがあります。何らかの原因で満足できなかったからこそクレームが入ります。もし相談室やコールセンターに1件も問い合わせがなかったとしたら、その製品の満足度は100%です。ただ実際にはそのようなことはありませんね。
近年はクレーム・問い合わせもビッグデータで経営資源であると言われています。これらのデータを満足性の特性に分類して件数を集計し、利用者がどこに不満を持っているかを分析して改善すれば解決します。ものづくりをする側は、いつの時代も新規性や高性能を追求しますが、利用者側はそれを望んでいるのでしょうか?満足しているのでしょうか?
私は年のせいなのか、最近のスマートフォンには違和感をおぼえます。最優先機能である電話が使いづらかったり(実用性)、すぐフリーズしたり(信用性)、アプリがよく分からず(快感性)、あまつさえ動きが遅かったり(快適性)と、利用時の品質である満足性は全く満たされていません。最後は年寄りの愚痴となりましたが、満足性についてはお分かりいただけましたでしょうか。それではまた次回。